この記事の目次
済美平成中等教育学校 × 電音エンジニアリング
文化祭を「学びの舞台」に変えたSTEAM教育の実装モデル
(注)STEAM教育:科学・技術・工学・芸術・数学を横断し、創造力で課題解決に向き合うための学習体系のこと。
全国で盛り上がる文化祭。
しかし、その多くは「発表の場」にとどまり、生徒の探究活動や学びのプロセスまでを、学習として可視化できている例は決して多くありません。
愛媛県の済美平成中等教育学校では2025年度、文部科学省の高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金(高等学校DX加速化推進事業)を活用し、文化祭そのものを「学びの場」へと進化させるプロジェクトに取り組みました。
生徒が主体となり、映像・音響・照明といったデジタル技術を活用しながら、自らの探究内容を他者に届ける「表現」へと昇華させる。その過程自体を学習と捉える、PBL型STEAM教育の実践です。
本記事では、生徒・教員・校長それぞれの言葉をもとに、この取り組みがどのように設計され、どのような学びを生み出したのかを紹介します。
●補助金制度を活用した、生徒主体の実践事例
●映像・音響・照明を「教育に組み込む」学習設計
●生徒主体の創造・協働・判断プロセスのリアル
●学校が安全・安心に導入できる支援体制
●文化祭を「一過性の行事」で終わらせないための要点
なぜ今、「演出 × 探究学習」が求められるのか
探究・STEAM教育が全国的に進む一方で、
「生徒のアイデアをどう形にし、どう発表し、どう社会と接続させるか」
という実装フェーズに課題を感じている学校は少なくありません。

済美平成中等教育学校では、この課題を次の3点に整理しました。
- 座学を超えた「体験知」を育みたい
- 生徒のアイデアをテクノロジーと結びつけたい
- 開校30周年に向け、学校全体で未来像を共有したい
そこで生まれたのが、
生徒主体で5分間のオープニング演出(プロジェクションマッピング)を制作するプロジェクトです。
学びが作品となり、作品が学校の未来像を示す。
探究と表現を橋渡しするモデルが、ここに設計されました。

補助金を「設備」ではなく「学び」に使うという判断
本プロジェクトでは、文部科学省の高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金を活用しています。
この制度の重要なポイントは、「生徒の主体的なデジタル活用による学習活動」そのものが補助対象となる点です。
完成品だけでなく、企画・試行錯誤・協働・改善といった制作プロセス自体が学習として評価される。この制度設計が、実践型STEAM教育を可能にしました。

プロジェクト概要
対象:5年生 10名
内容:映像・音響・照明を用いたオープニング演出制作
体制:生徒主体(班制)+ 電音エンジニアリング伴走
期間:2025年7月〜10月
(定例ミーティング/現地授業/本番サポート)
本番:10月31日 文化祭オープニング(約5分)
生徒が「創る」構造が、そのまま学びになる
本プロジェクトでは、生徒自身が「何を作りたいのか」を起点に企画を立て、役割を分担しながら制作を進めました。
制作チーム構成は、
・ディレクター 1名
・映像撮影 3名
・映像編集 3名
・美術 3名責任、協働、判断、改善。
社会に近いプロセスそのものが学習になります。

電音エンジニアリングの役割
電音エンジニアリングは、作品づくりの主体を常に生徒に置き、担当教員の指導方針に沿って、
● 技術的な相談
● 安全面の配慮
● 実施環境の整備
を中心にサポートしました。
専門知識は共有しますが、最終的な判断は生徒が行う。
この前提を崩さないことを重視しています。
環境課題も「学び」に変える
体育館は遮光設備が十分でなく、プロジェクションマッピングには不利な条件でした。
暗幕による局所遮光、高輝度プロジェクター、照明調整。
制約条件をどう乗り越えるかも学習の一部として扱いました。

ここから先は、現場の声です
ここから先では、本プロジェクトに実際に関わった生徒・担当教員・校長の声を紹介します。
企画や学習設計として整理してきた内容が、現場でどのように受け止められ、どのような学びとして立ち上がっていったのか。当事者の言葉を通して、その実感を追っていきます。
生徒インタビュー|「つくる側」に立ったという実感

本プロジェクトに参加した生徒たちは、 単に映像を制作したのではなく、「誰に、何を、どう伝えるか」を考える側として関わりました。参加のきっかけや、プロジェクト初期に感じていた思いは、それぞれに異なっていました。
「門屋先生に声をかけてもらって、自分が興味をもっていた分野だったので即答でした。」(忽那さん)
「初めてのMTGで、これは大きなプロジェクトになるという期待感と責任感が湧いた。」(岡さん)
制作が進むにつれ、生徒たちは思い通りにいかない現実にも直面します。
「構成を意識した撮影ができず映像に一貫性がなかったが、全員で解決案を出して乗り切った。」(杉下さん)
その過程で、自分の役割だけでなく、チーム全体を見渡す視点も育っていきました。
「誰にも頼まれていないのに、撮影スケジュールを整理して共有してくれた。」(伊藤さん)
そして迎えた本番。
完成した演出を通して、生徒たちは確かな手応えを得ます。
「本番中の生徒の反応が嬉しくて、このプロジェクトの素晴らしさを改めて実感した。」(吉田さん)
「いいものを作ろうと思わないといいものは作れない。そういうマインドを持つことの大切さを学びました。」(中野さん)
これらの言葉は、 生徒たちが「表現する側」「つくる側」として文化祭に関わった証でもあります。
学習設計者・担当教員(門屋先生)インタビュー
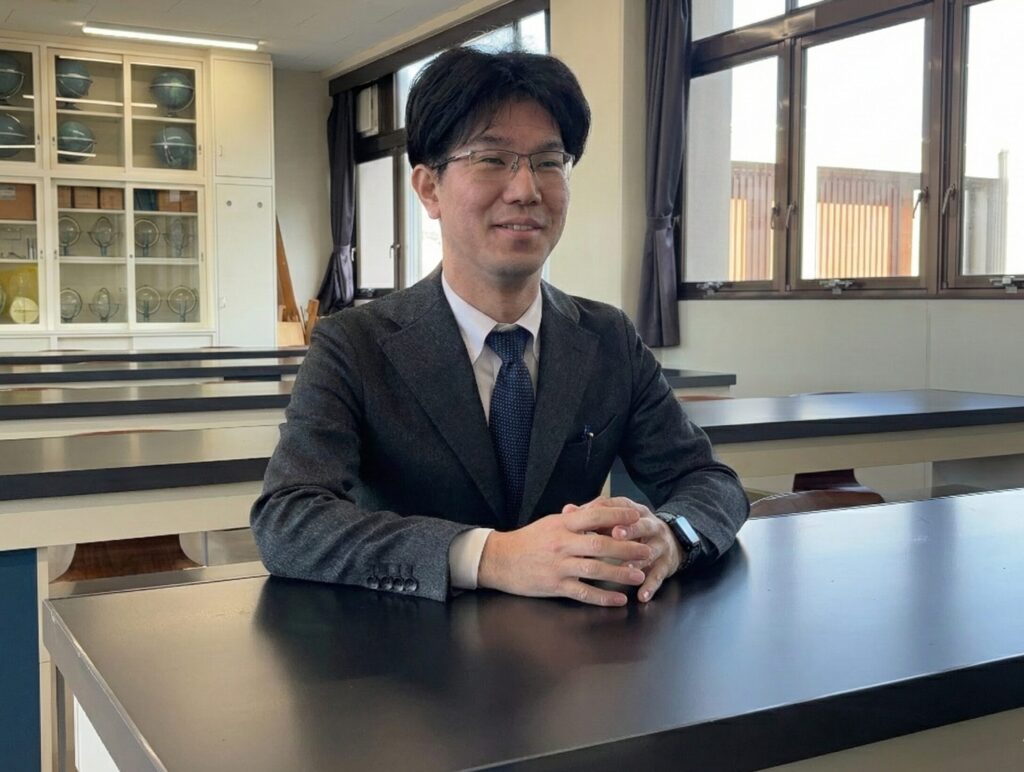
本プロジェクトの立ち上げから学習設計、現場運営までを担ったのが、担当教員の門屋先生です。
門屋先生は、この取り組みを単なる体験型イベントではなく、DXハイスクールの趣旨に沿った教育実践として位置づけ、構想段階から深く関わってきました。
DXハイスクールの補助金を活用するにあたり、どれだけ教育的価値の高い取り組みができるかを模索していました。
単なる一過性の体験ではなく、形として残り、生徒の記憶や学びに深く刻まれるものの方が、学習効果も高いと考えたからです。
また、可能であれば全校生徒が関われる取り組みにしたいという思いもあり、情報収集を進めていました。
そうした中で出会ったのが、宝仙学園小学校で行われていたプロジェクションマッピングの事例です。小学生が主体的に企画・制作に関わり、非常に完成度の高い作品を作り上げている姿を見て、大きな衝撃を受けました。
「小学生でここまでできるのなら、高校生であれば、より高度な表現や技術的な挑戦ができるのではないか」
「そのプロセス自体が、DX人材育成やSTEAM教育の観点からも非常に価値のある体験になるのではないか」
そう強く感じたことが、今回の取り組みにつながっています。
デジタル技術を単に「使う」だけでなく、課題設定から表現、協働、アウトプットまでを一貫して経験できる学びとして、このプロジェクトはDXハイスクールの趣旨にも合致しており、生徒にとって大きな成長機会になると確信しました。
生徒主体とはいえ、生徒が自由に動ける範囲にはどうしても制約があります。
そこで、生徒が「考えること」「挑戦すること」に集中できるよう、環境面の整備や事前調整を大人がしっかり担うことを重視しました。
例えば撮影に関しては、生徒が個別に許可取りを行う前段階で、各部活動の顧問の先生方に趣旨やスケジュールを事前に共有し、現場でのやり取りが滞らないよう配慮しました。
こうした裏側の調整を大人が支えることで、生徒の主体的な活動がスムーズに進むと考えたからです。
もう一つ大切にしたのは、プロフェッショナルが本気で関わっている現場であることを、生徒に実感させることでした。
DXハイスクールの取り組みでは、デジタル技術そのもの以上に、社会で通用する仕事の姿勢やプロセスを体感することが重要だと感じています。
大人が本気で取り組む姿、プロが妥協せずに制作に向き合う姿勢は、生徒に強い影響を与えます。そうした環境の中で活動することで、生徒たちの意識やアウトプットの質も大きく変わっていくと考えていました。
実は、あらかじめ「この学びを得てほしい」という狙いを一つに定めていたわけではありませんでした。むしろ、生徒一人ひとりの関わり方によって、多様な学びや気づきが自然に生まれてくるだろうと考えていました。
その中で、特に印象に残ったのが、課題に直面した際の思考や行動、いわゆる問題解決力の部分での成長です。制作を進める過程では、思い通りにいかない場面や予期せぬトラブルも多く発生しましたが、生徒たちはその都度、自分たちで原因を考え、役割分担を見直し、解決策を模索していきました。その姿は、当初こちらが想像していた以上のものでした。
DXハイスクールが目指す「デジタル技術を活用しながら、試行錯誤を通じて課題を解決していく力」が、机上の学習ではなく、実践的なプロジェクトを通して確かに育まれていたと感じています。正解のない問いに向き合い、考え、行動する。そのプロセス自体が、生徒にとって大きな学びになったのではないでしょうか。
プロジェクトが本格化し、生徒たちが「本気でいいものを作りたい」と思うようになった頃から、一人では物事を進められないという意識が自然と芽生えてきたように感じました。
その結果、報告・連絡・相談、いわゆるホウレンソウを密に取り合う姿が、これまで以上に見られるようになりました。
制作の現場では、誰か一人の判断や作業の遅れが全体に影響します。
そうした経験を通して、生徒たちは「情報を共有すること」「状況を言語化して伝えること」の重要性に気づいていったのだと思います。
指示されたからではなく、目的達成のために自発的にコミュニケーションを取るようになった。その変化は、このプロジェクトを象徴する場面の一つでした。
電音エンジニアリングとの連携で大きかったのは、求められるクオリティの高さと、技術的な完成度の基準を、生徒が肌で感じられたことです。
単に映像を作る、動かすということではなく、なぜこの構成なのか、なぜこの動きが必要なのかといった点まで、常にプロの視点からフィードバックが入ることで、生徒たちの意識が大きく変わっていきました。
特に印象的だったのは、緻密な設定や動きに対するこだわりです。
一見すると分からないような細部にまで意味があり、全体の演出やメッセージ性を高めるために調整が重ねられていく。そのプロセスを間近で見ることで、生徒たちは「クオリティとは何か」「技術を使うとはどういうことか」を具体的に理解していったように思います。
DXハイスクールの取り組みとしても、高度なデジタル技術を、実社会の水準でどう活用するのかを体感できたことは、非常に大きな学びでした。
プロと同じ目線で作品づくりに向き合う経験は、技術習得にとどまらず、物事に向き合う姿勢そのものを学ぶ機会になったと感じています。
また、選択肢がまったくなかったわけではありませんが、これまでの実績を通して築かれてきた信頼感があったことで、自然と電音エンジニアリングにお願いする流れになりました。
単に技術力が高いというだけでなく、学校教育の文脈を理解した上で伴走してくれる点は、他社にはない強みだと感じています。企画段階から現場運営、最終的なアウトプットに至るまで、一つひとつ丁寧に向き合ってもらえるという安心感がありました。生徒主体で進める今回のようなプロジェクトでは、想定外のことも多く起こります。
その中で、柔軟に対応しながらも、クオリティを落とさずに支えてもらえるパートナーであることが、依頼の決め手になったと思います。
今回の取り組みは、教育的な効果が非常に大きかったと感じています。
生徒たちの中にあったのは、「作品を残したい」「自分たちの手で何かを作り上げたい」という、非常にシンプルな思いでした。
その内発的な動機こそが、この取り組みの出発点であり、探究学習の核だったと感じています。
映像やデジタル技術を手段として活用しながら、何を表現したいのか、どうすれば伝わるのかを自ら考え、試行錯誤するプロセスを重ねていく。
理科・技術・芸術といった複数の要素が横断的に関わり、まさにSTEAM教育の実践そのものだったと思います。
完成した作品がその場限りで終わるのではなく、形として残り、誰かに見られ、評価されるものになる。この経験は、生徒の学びをより確かなものにしました。
来年度以降は、今年の経験を土台にしながら、より規模の大きなプロジェクトや、より高度な表現・技術に挑戦する取り組みへと発展させていきたいと考えています。
DXハイスクールの枠組みを活用しながら、教育的価値と学校の魅力向上の両立を図り、継続的な取り組みとして育てていければと思っています。
校長先生|文化祭を「未来につながる学び」へ

校長先生は、本プロジェクトを学校全体の視点から次のように位置づけています。
文化祭のオープニングとして披露された今回の演出は、「これからワクワクする時間が始まる」というメッセージを、生徒自身の手で表現したものでした。
生徒会を中心とした要望を取り入れながら、電音エンジニアリングさんのプロの技によって、その意図が見事に形になったと感じています。
完成度が非常に高く、出演者も観客も大きな満足感を得ることができました。
プロの方々が、本気で仕事に向き合う姿は、生徒にとって何よりの学びだったと思います。
また、校長先生は現場に立ち会った立場から、次のようなメッセージも寄せてくださいました。
「電音エンジニアリングのスタッフの皆さん、お世話になりました。スタッフの方々の様子を傍らで見させていただいて、いつも笑顔でおられることが印象的でした。そして気持ちの良い挨拶を常に教職員はもちろんのこと、生徒諸君にして下さいました。スタッフの方々もリラックスする際は大いにリラックスし、そして仕事をする時は、プロ意識を全面に出した究極の集中をされていたのではないでしょうか。ともあれ、最終的に大いに楽しんで下さったのではないか、と思っています。本当にありがとうございました。」
一過性のイベントから、学校独自の「学習資産」へ

文化祭の演出を生徒主体で行うことは、単なる思い出づくりではありません。
- ● 次世代へ継承される知識と技術
- ● 制約を乗り越える課題解決文化
- ● 公共空間で表現する自己効力感
探究を「表現」へ。学びを、他者に届く形へ。
ご関心のある学校様へ
電音エンジニアリングでは、学校の教育方針・規模・環境に応じた
段階導入・学習設計・安全面を含む伴走支援を行っています。
生徒主体の学びを、確かな形で実装したい場合は、ぜひご相談ください。
関連記事




